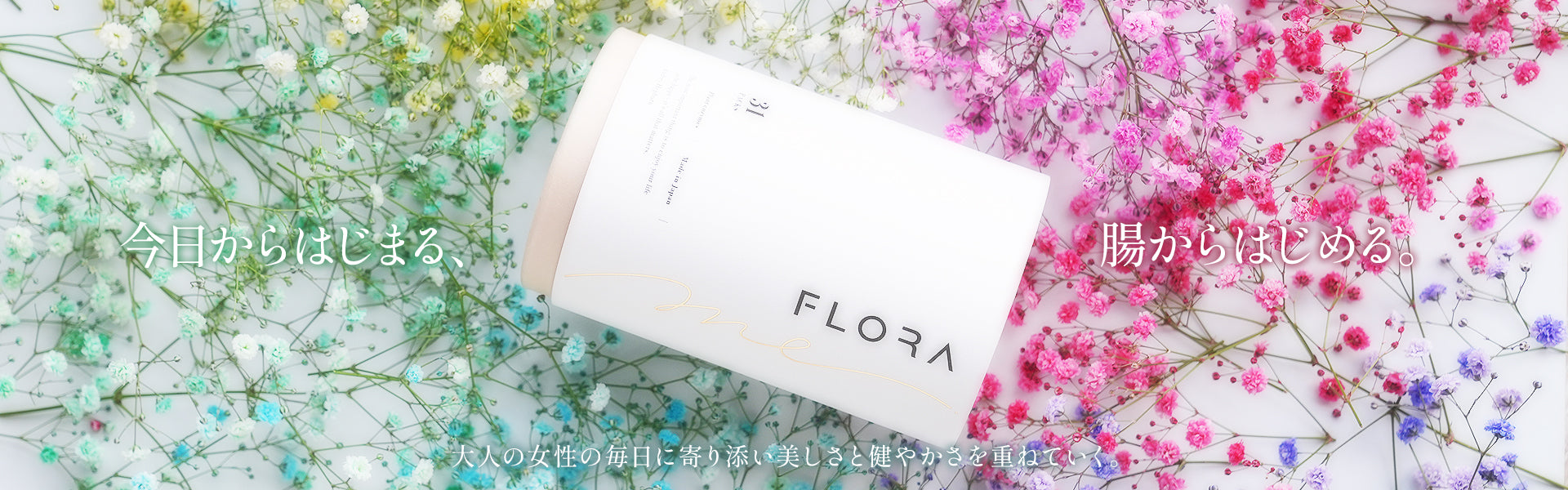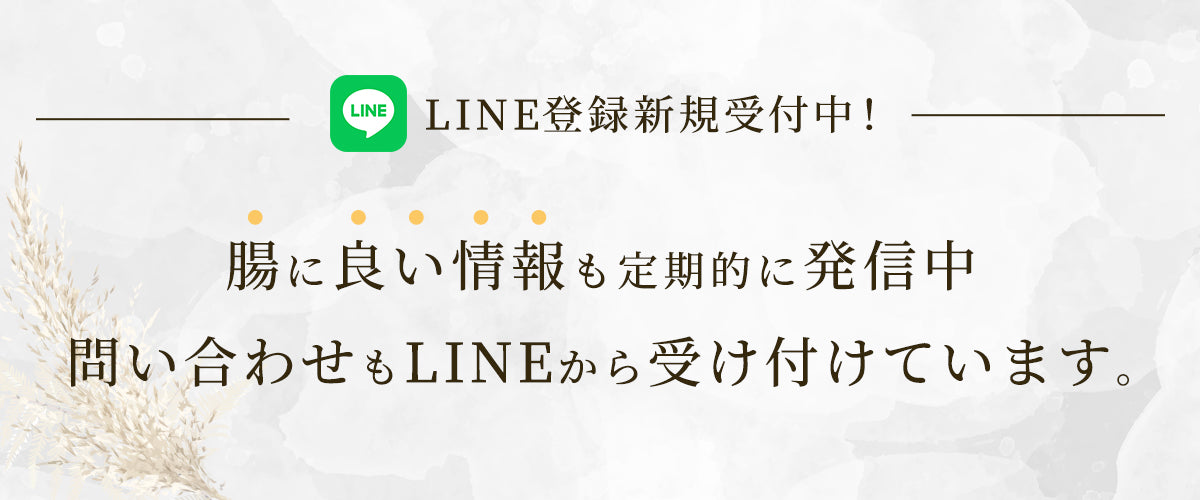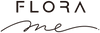コラム

便秘改善の腸活法 STEP3
前々回のコラム「便秘改善の腸活法 STEP1」では、腸活をおこなう上でまずは抑えておきたい、「腸が嫌がることを減らし、腸が喜ぶことを増やす」の大切さとその例について説明をしてきました。 そして、前回のコラム「便秘改善の腸活法 STEP2」では「腸の温活」「適度な水分の摂取」「食物繊維を摂る」といった取り組みやすい腸活法について説明をしてきました。 ぜひ、この2つのSTEPも参考に取り組んで頂ければと思います。 【便秘の改善方法 STEP3】 今回のSTEP3においては、前回と同様に腸が喜ぶことについて紹介をしていきます。腸活の基本は、腸が嫌がることを減らし、腸が喜ぶことを増やすが基本になります。腸が喜ぶこととは、腸内が善玉菌優位な腸内環境になること、また腸が働きやすい環境にすることです。 ◆善玉菌を摂る 善玉菌は、私たちにとって様々な良い働きをします。・腸内を弱酸性にすることで悪玉菌が増えないようにします。・腸のぜんどう運動を促進して、排便力を高めます。・ビタミンB群やビタミンKなど、身体の代謝に有益な栄養をつくります。・腸の免疫系を刺激し、免疫機能をサポートします。 このように善玉菌は、腸や身体にとってプラスの働きをすることから、便通を良くしてくれる働きがあります。 昔からヨーグルトの乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌が腸に良いということは、聞いたことがあると思います。 このように発酵食品には、善玉菌が豊富に含まれているため、日常から発酵食品を摂っていくことがオススメです。 日常で取り入れやすい発酵食品は、以下になります。 ・納豆納豆の納豆菌は、生きたまま腸に届き、悪玉菌を抑制し善玉菌を増やします。納豆に醤油麹を加えて食べるのがオススメです。 ・味噌(味噌汁)味噌には、麹菌、酵母菌、乳酸菌が含まれています。野菜味噌汁で摂ると野菜の食物繊維と合わせて善玉菌を増やしてくれます。 ・キムチ発酵をしているキムチには、乳酸菌が含まれており、また野菜の食物繊維も同時に摂ることが出来ます。注意点は、パッケージに「発酵」という言葉や「キムチくんマーク」があるキムチを選びましょう。 ・ぬか漬けぬか漬けには、乳酸菌や食物繊維が含まれているためオススメの発酵食品です。最近では、ぬか漬けキットも販売されているため、自宅でも作りやすくなっています。 ・ヨーグルト便通をよくするためにヨーグルトを食べる際は、ビフィズス菌が含まれているヨーグルトを選びましょう。乳酸菌よりもビフィズス菌の方が大腸内で有効な働きをしてくれます。 これ以外にも調味料として、醤油麹、塩麹、お酢、醤油などを料理に合わせて摂ることも意識していきましょう。 ただ注意点として、発酵食品の摂り過ぎは、炎症の原因になったり、善玉菌の増えすぎはSIBOと言われる病気の元になることがあります。あくまでも腸内細菌は、善玉菌と悪玉菌と日和見菌のバランスが大切になるので、腸の様子を見ながら過度に摂り過ぎないようにしましょう。 ◆間食には腸に良いものを 食事と食事の間の間食、特に昼食と夕食の間食として白砂糖や添加物が含まれたお菓子などを食べる人もいると思います。 時たま、お菓子を食べるぐらいであれば、影響は少ないかもしれませんが、毎日たくさん食べているようであれば、腸内環境を乱す一因になっていると思います。 出来れば、この間食も腸活として便通に効果のある食べ物を摂っていくと便通改善に効果的になります。 ・干し芋干し芋は、さつまいもを蒸して乾燥させたもので、さつまいもの栄養素が凝縮して詰まっています。食物繊維が豊富でかつ、水溶性食物繊維も豊富になります。更にビタミンやミネラルやカリウムといった栄養が含まれ、血糖値も上げずらい腸活に良い間食の食べ物になります。砂糖不使用のものを選びましょう。 ・ドライなつめなつめは、ビタミンB群やミネラル、また食物繊維が豊富な食べ物になります。食物繊維はごぼうの2倍以上も含まれています。中国では、1日に3個食べると老いないとも言われ、漢方に使われるほど。こちらも砂糖不使用なものを選びましょう。 ・甘酒甘酒は、飲む点滴と呼ばれるほど、身体にも腸にも良い飲み物になります。ビタミン、ミネラル、アミノ酸といった栄養以外にも、善玉菌を育てる働きや食物繊維と似た働きをするレジスタントプロテインと呼ばれるものも含まれています。間食のおやつとしてぜひ飲んでみて下さい。 ・ドライプルーンドライプルーンもビタミンやミネラルといった栄養を豊富に含み、また水溶性と不溶性の食物繊維を約50%ずつバランス良く含みます。ただ、プルーンは、摂り過ぎるとお腹を下すこともあるので摂り過ぎには注意が必要です。 ・バナナバナナには、善玉菌のエサとなるオリゴ糖やレジスタントスターチと呼ばれる成分が含まれており、善玉菌を増やす効果があります。ただ熟したバナナは、レジスタントスターチが減少してくるので熟す前のバナナを選びましょう。 ・ナッツ類アーモンド、クルミ、ピスタチオは、食物繊維を豊富に含み、腸活に良い食べ物です。クルミには、身体にいい油のオメガ3脂肪酸も含まれています。ナッツ類だけでは少し物足りない場合は、ドライなつめやドライプルーン、またドライいちじくなども一緒に食べても良いでしょう。 ・その他果物紹介した以外にも果物には、食物繊維やビタミンなどの栄養を豊富に含みます。また消化負担も軽いことから、間食に適しています。ただ、果糖は血糖値上昇、また糖化という別の悪影響もあるため、果物も食べ過ぎには注意が必要で1日200gを目安としましょう。 このように間食のおやつを上手く活用するとしっかりと腸活ができ、便通が良くなりますね。ぜひ試してみましょう。...
便秘改善の腸活法 STEP3
前々回のコラム「便秘改善の腸活法 STEP1」では、腸活をおこなう上でまずは抑えておきたい、「腸が嫌がることを減らし、腸が喜ぶことを増やす」の大切さとその例について説明をしてきました。 そして、前回のコラム「便秘改善の腸活法 STEP2」では「腸の温活」「適度な水分の摂取」「食物繊維を摂る」といった取り組みやすい腸活法について説明をしてきました。 ぜひ、この2つのSTEPも参考に取り組んで頂ければと思います。 【便秘の改善方法 STEP3】 今回のSTEP3においては、前回と同様に腸が喜ぶことについて紹介をしていきます。腸活の基本は、腸が嫌がることを減らし、腸が喜ぶことを増やすが基本になります。腸が喜ぶこととは、腸内が善玉菌優位な腸内環境になること、また腸が働きやすい環境にすることです。 ◆善玉菌を摂る 善玉菌は、私たちにとって様々な良い働きをします。・腸内を弱酸性にすることで悪玉菌が増えないようにします。・腸のぜんどう運動を促進して、排便力を高めます。・ビタミンB群やビタミンKなど、身体の代謝に有益な栄養をつくります。・腸の免疫系を刺激し、免疫機能をサポートします。 このように善玉菌は、腸や身体にとってプラスの働きをすることから、便通を良くしてくれる働きがあります。 昔からヨーグルトの乳酸菌やビフィズス菌といった善玉菌が腸に良いということは、聞いたことがあると思います。 このように発酵食品には、善玉菌が豊富に含まれているため、日常から発酵食品を摂っていくことがオススメです。 日常で取り入れやすい発酵食品は、以下になります。 ・納豆納豆の納豆菌は、生きたまま腸に届き、悪玉菌を抑制し善玉菌を増やします。納豆に醤油麹を加えて食べるのがオススメです。 ・味噌(味噌汁)味噌には、麹菌、酵母菌、乳酸菌が含まれています。野菜味噌汁で摂ると野菜の食物繊維と合わせて善玉菌を増やしてくれます。 ・キムチ発酵をしているキムチには、乳酸菌が含まれており、また野菜の食物繊維も同時に摂ることが出来ます。注意点は、パッケージに「発酵」という言葉や「キムチくんマーク」があるキムチを選びましょう。 ・ぬか漬けぬか漬けには、乳酸菌や食物繊維が含まれているためオススメの発酵食品です。最近では、ぬか漬けキットも販売されているため、自宅でも作りやすくなっています。 ・ヨーグルト便通をよくするためにヨーグルトを食べる際は、ビフィズス菌が含まれているヨーグルトを選びましょう。乳酸菌よりもビフィズス菌の方が大腸内で有効な働きをしてくれます。 これ以外にも調味料として、醤油麹、塩麹、お酢、醤油などを料理に合わせて摂ることも意識していきましょう。 ただ注意点として、発酵食品の摂り過ぎは、炎症の原因になったり、善玉菌の増えすぎはSIBOと言われる病気の元になることがあります。あくまでも腸内細菌は、善玉菌と悪玉菌と日和見菌のバランスが大切になるので、腸の様子を見ながら過度に摂り過ぎないようにしましょう。 ◆間食には腸に良いものを 食事と食事の間の間食、特に昼食と夕食の間食として白砂糖や添加物が含まれたお菓子などを食べる人もいると思います。 時たま、お菓子を食べるぐらいであれば、影響は少ないかもしれませんが、毎日たくさん食べているようであれば、腸内環境を乱す一因になっていると思います。 出来れば、この間食も腸活として便通に効果のある食べ物を摂っていくと便通改善に効果的になります。 ・干し芋干し芋は、さつまいもを蒸して乾燥させたもので、さつまいもの栄養素が凝縮して詰まっています。食物繊維が豊富でかつ、水溶性食物繊維も豊富になります。更にビタミンやミネラルやカリウムといった栄養が含まれ、血糖値も上げずらい腸活に良い間食の食べ物になります。砂糖不使用のものを選びましょう。 ・ドライなつめなつめは、ビタミンB群やミネラル、また食物繊維が豊富な食べ物になります。食物繊維はごぼうの2倍以上も含まれています。中国では、1日に3個食べると老いないとも言われ、漢方に使われるほど。こちらも砂糖不使用なものを選びましょう。 ・甘酒甘酒は、飲む点滴と呼ばれるほど、身体にも腸にも良い飲み物になります。ビタミン、ミネラル、アミノ酸といった栄養以外にも、善玉菌を育てる働きや食物繊維と似た働きをするレジスタントプロテインと呼ばれるものも含まれています。間食のおやつとしてぜひ飲んでみて下さい。 ・ドライプルーンドライプルーンもビタミンやミネラルといった栄養を豊富に含み、また水溶性と不溶性の食物繊維を約50%ずつバランス良く含みます。ただ、プルーンは、摂り過ぎるとお腹を下すこともあるので摂り過ぎには注意が必要です。 ・バナナバナナには、善玉菌のエサとなるオリゴ糖やレジスタントスターチと呼ばれる成分が含まれており、善玉菌を増やす効果があります。ただ熟したバナナは、レジスタントスターチが減少してくるので熟す前のバナナを選びましょう。 ・ナッツ類アーモンド、クルミ、ピスタチオは、食物繊維を豊富に含み、腸活に良い食べ物です。クルミには、身体にいい油のオメガ3脂肪酸も含まれています。ナッツ類だけでは少し物足りない場合は、ドライなつめやドライプルーン、またドライいちじくなども一緒に食べても良いでしょう。 ・その他果物紹介した以外にも果物には、食物繊維やビタミンなどの栄養を豊富に含みます。また消化負担も軽いことから、間食に適しています。ただ、果糖は血糖値上昇、また糖化という別の悪影響もあるため、果物も食べ過ぎには注意が必要で1日200gを目安としましょう。 このように間食のおやつを上手く活用するとしっかりと腸活ができ、便通が良くなりますね。ぜひ試してみましょう。...

便秘改善の腸活法 STEP2
前回のコラム「便秘改善の腸活法 STEP1」では、腸活をおこなう上でまずは抑えておきたい、腸活の基本とSTEP1の腸が嫌がることを減らす、について説明をしてきました。 腸活を成功させるには、腸活の基本とSTEP1が大切になるため、そちらをまずは試して頂きたいと思います。 ◆便秘の改善方法 STEP2 腸が嫌がることを減らすことが出来たら、次は腸が喜ぶことを増やすステップになります。腸が喜ぶこととは、腸内が善玉菌優位な腸内環境になること、また腸が働きやすい環境にすることです。 ◆腸の温活 身体を温める温活が健康に良い、ということは誰もが聞いたことがあると思います。身体の中でも特に腸を温める腸の温活をおこなうことで、お腹周りの血行促進に繋がり、腸本来の働きを引き出すことに繋がります。 腸温活の例 ・白湯を飲むことで胃腸を一時的に温めることが出来ます。 ・シャワーだけでなく、30度~40度の湯船に10分以上浸かる。 ・カイロなどをお腹に貼って温める。 ・腹巻をしてお腹を温める。 ・生姜紅茶を飲んで温める。 ・身体を温める熱性や温性の食材を食べる(にんにく、生姜、南瓜、ねぎ、ニラ、たまねぎ、胡椒、鶏肉、エビなど) ・運動をして身体全身の血流を良くしてお腹を温める。 ・よもぎ蒸しでお腹を温める。 また反対に冷たい飲み物や食べ物は避けたり、夏の冷房の温度を気を付けたり、お腹周りが冷えるような服は避けるなども必要です。 ◆適度な水分の摂取 便の中の水分が少ないと便が固くなり、便秘になりやすくなります。日常での水分摂取量が少ないとそれが便秘に繋がっている可能性が考えられます。 そのため、自分の体格や日頃の運動量に応じた、適した水分摂取をおこなうことが大切です。 目安としては、体重(kg)×30ml~35mになります。 例えば、体重50kgであれば50×35mlは、1750mlになります。 この摂取量は、食事からの摂取も含まれた量になり、3食で20%~30%を摂取していると言われています。そのため、残りの70%~80%を水やお茶などのドリンクから摂ることが大切です。 力仕事やスポーツをおこなう活動量が多い方、また夏の暑い時期によく汗をかく方などは、適量がもう少し多くなるはずですね。 ご自身の体格(体重)や活動量を踏まえて、適した水分摂取量を概算してみて下さい。 最終的な判断は、ご自身のお腹や身体の調子を見ながら、適した摂取量を見つけていきましょう。 ただ、冷たい飲み物は、腸を冷やしてしまうので常温水や温かい飲み物を摂るように心がけます。...
便秘改善の腸活法 STEP2
前回のコラム「便秘改善の腸活法 STEP1」では、腸活をおこなう上でまずは抑えておきたい、腸活の基本とSTEP1の腸が嫌がることを減らす、について説明をしてきました。 腸活を成功させるには、腸活の基本とSTEP1が大切になるため、そちらをまずは試して頂きたいと思います。 ◆便秘の改善方法 STEP2 腸が嫌がることを減らすことが出来たら、次は腸が喜ぶことを増やすステップになります。腸が喜ぶこととは、腸内が善玉菌優位な腸内環境になること、また腸が働きやすい環境にすることです。 ◆腸の温活 身体を温める温活が健康に良い、ということは誰もが聞いたことがあると思います。身体の中でも特に腸を温める腸の温活をおこなうことで、お腹周りの血行促進に繋がり、腸本来の働きを引き出すことに繋がります。 腸温活の例 ・白湯を飲むことで胃腸を一時的に温めることが出来ます。 ・シャワーだけでなく、30度~40度の湯船に10分以上浸かる。 ・カイロなどをお腹に貼って温める。 ・腹巻をしてお腹を温める。 ・生姜紅茶を飲んで温める。 ・身体を温める熱性や温性の食材を食べる(にんにく、生姜、南瓜、ねぎ、ニラ、たまねぎ、胡椒、鶏肉、エビなど) ・運動をして身体全身の血流を良くしてお腹を温める。 ・よもぎ蒸しでお腹を温める。 また反対に冷たい飲み物や食べ物は避けたり、夏の冷房の温度を気を付けたり、お腹周りが冷えるような服は避けるなども必要です。 ◆適度な水分の摂取 便の中の水分が少ないと便が固くなり、便秘になりやすくなります。日常での水分摂取量が少ないとそれが便秘に繋がっている可能性が考えられます。 そのため、自分の体格や日頃の運動量に応じた、適した水分摂取をおこなうことが大切です。 目安としては、体重(kg)×30ml~35mになります。 例えば、体重50kgであれば50×35mlは、1750mlになります。 この摂取量は、食事からの摂取も含まれた量になり、3食で20%~30%を摂取していると言われています。そのため、残りの70%~80%を水やお茶などのドリンクから摂ることが大切です。 力仕事やスポーツをおこなう活動量が多い方、また夏の暑い時期によく汗をかく方などは、適量がもう少し多くなるはずですね。 ご自身の体格(体重)や活動量を踏まえて、適した水分摂取量を概算してみて下さい。 最終的な判断は、ご自身のお腹や身体の調子を見ながら、適した摂取量を見つけていきましょう。 ただ、冷たい飲み物は、腸を冷やしてしまうので常温水や温かい飲み物を摂るように心がけます。...

便秘改善の腸活法 STEP1
◆日本における便秘の状況 日本における便秘の有訴者数は、約431万5000人にもなり、年齢が高くなるほどその割合が大きくなります。実際に腸活におけるアドバイスをしていく中で最も多い質問が便秘に関するお悩みになります。 2019年 国民基礎調査より ◆腸活の基本 腸活を始める前に腸活の基本を先にお話しいたします。基本を知らずに腸活を初めて、効果が感じずに失敗をすることがよくありますので注意が必要です。 反対に基本を知っておくことで腸活の成功に繋がりやすくなります。 ①一つの方法を2週間ほど試して、自分の腸に合っているかどうかを判断する 一つの腸活法を試して、翌日から腸の調子が良くなるということは、ほとんどありません。一つの腸活法を2週間ほど試して、腸内環境が良くなったかどうかを自分の体感や便の状態を見ながら、判断をしていきます。 腸内環境は、一人一人異なるため、万人に効果のある腸活法というものは存在せず、自分にあった方法を自分の腸の声を聞きながら見つけていくことが大切です。 ②腸活法を一つずつ試してみる 腸活法を一度に全てやり始めて、腸の調子が良くなったとしても、どの方法によって腸内環境が改善されたのかを把握することが出来ません。 腸活法は一つずつ試して、どの方法が腸内環境の改善に繋がったのかを把握していきましょう。 ③やり過ぎに注意して、適量を心がける どんなに良い方法もやり過ぎは、反対にマイナスの効果になります。例えば、食物繊維が腸活に効果的ということで、食物繊維ばかりを摂り過ぎると下痢や便秘に繋がります。どんな方法も適量を心がけ、自分の適量は自分の腸の承知で判断をしていきます。 ④完璧を求めない 腸活法は、多岐に渡ります。その全てを完璧におこなおうとすると生活への影響が出て、ストレスが溜まり、反対に腸の調子を崩すことに繋がります。完璧を求めずに少し気を楽に始めてみましょう。 ◆便秘の改善方法 STEP1 便秘の改善に向けた腸活法は、ライフスタイル全体に及び、かなり範囲が広くなりますがSTEP1、STEP2、STEP3、STEP4の4回のコラムに分けて紹介をしていきます。 STEP1 腸活は、腸が嫌がることを減らし、腸が喜ぶことを増やすことが大切になります。順番として、まずは腸が嫌がることを減らしていくことで、その後の腸が喜ぶことの効果がより高くなります。 <腸が嫌がることの例> ①冷たい飲み物をよく飲む、冷たい食べ物をよく食べる胃腸が冷えて、腸が委縮し、本来の働きが十分できなくなります。 ②暴飲暴食消化のキャパシティをこえてしまい、胃腸への負担が大きくなります。 ③白砂糖を多く含む、清涼飲料水やお菓子、菓子パンをよく食べる白砂糖が悪玉菌のエサとなり、腸内環境を乱してしまいます。 ④早食い咀嚼が疎かになり、消化不良で胃腸への負担が大きくなります。 ⑤肉類をよく食べるたんぱく質は、とても大切な栄養素ですが、未消化のたんぱく質が悪玉菌を増やしてしまいます。 ⑥食品添加物を多く含む加工食品をよく食べる食品添加物は、胃腸での消化負担になり、また腸内細菌の多様性を阻害します。 ⑦パンや麺類など小麦製品をよく食べる小麦製品をよく食べると小麦に含まれるグルテンが、腸内環境を乱してしまいます。...
便秘改善の腸活法 STEP1
◆日本における便秘の状況 日本における便秘の有訴者数は、約431万5000人にもなり、年齢が高くなるほどその割合が大きくなります。実際に腸活におけるアドバイスをしていく中で最も多い質問が便秘に関するお悩みになります。 2019年 国民基礎調査より ◆腸活の基本 腸活を始める前に腸活の基本を先にお話しいたします。基本を知らずに腸活を初めて、効果が感じずに失敗をすることがよくありますので注意が必要です。 反対に基本を知っておくことで腸活の成功に繋がりやすくなります。 ①一つの方法を2週間ほど試して、自分の腸に合っているかどうかを判断する 一つの腸活法を試して、翌日から腸の調子が良くなるということは、ほとんどありません。一つの腸活法を2週間ほど試して、腸内環境が良くなったかどうかを自分の体感や便の状態を見ながら、判断をしていきます。 腸内環境は、一人一人異なるため、万人に効果のある腸活法というものは存在せず、自分にあった方法を自分の腸の声を聞きながら見つけていくことが大切です。 ②腸活法を一つずつ試してみる 腸活法を一度に全てやり始めて、腸の調子が良くなったとしても、どの方法によって腸内環境が改善されたのかを把握することが出来ません。 腸活法は一つずつ試して、どの方法が腸内環境の改善に繋がったのかを把握していきましょう。 ③やり過ぎに注意して、適量を心がける どんなに良い方法もやり過ぎは、反対にマイナスの効果になります。例えば、食物繊維が腸活に効果的ということで、食物繊維ばかりを摂り過ぎると下痢や便秘に繋がります。どんな方法も適量を心がけ、自分の適量は自分の腸の承知で判断をしていきます。 ④完璧を求めない 腸活法は、多岐に渡ります。その全てを完璧におこなおうとすると生活への影響が出て、ストレスが溜まり、反対に腸の調子を崩すことに繋がります。完璧を求めずに少し気を楽に始めてみましょう。 ◆便秘の改善方法 STEP1 便秘の改善に向けた腸活法は、ライフスタイル全体に及び、かなり範囲が広くなりますがSTEP1、STEP2、STEP3、STEP4の4回のコラムに分けて紹介をしていきます。 STEP1 腸活は、腸が嫌がることを減らし、腸が喜ぶことを増やすことが大切になります。順番として、まずは腸が嫌がることを減らしていくことで、その後の腸が喜ぶことの効果がより高くなります。 <腸が嫌がることの例> ①冷たい飲み物をよく飲む、冷たい食べ物をよく食べる胃腸が冷えて、腸が委縮し、本来の働きが十分できなくなります。 ②暴飲暴食消化のキャパシティをこえてしまい、胃腸への負担が大きくなります。 ③白砂糖を多く含む、清涼飲料水やお菓子、菓子パンをよく食べる白砂糖が悪玉菌のエサとなり、腸内環境を乱してしまいます。 ④早食い咀嚼が疎かになり、消化不良で胃腸への負担が大きくなります。 ⑤肉類をよく食べるたんぱく質は、とても大切な栄養素ですが、未消化のたんぱく質が悪玉菌を増やしてしまいます。 ⑥食品添加物を多く含む加工食品をよく食べる食品添加物は、胃腸での消化負担になり、また腸内細菌の多様性を阻害します。 ⑦パンや麺類など小麦製品をよく食べる小麦製品をよく食べると小麦に含まれるグルテンが、腸内環境を乱してしまいます。...

他に類を見ない酵素ペーストでの3次発酵を実現!
一般的に酵素ぺーストや酵素ドリンクは、発酵や熟成によって作られますが、その品質は様々で中には、自然の発酵ではなく、人工的に発酵を早め、熟成期間も1ヶ月しかないというような製品もあります。 反対にフローラミーは、自然の力に任せて、8年にも及ぶ熟成期間を経て作られています。 熟成期間に入る前までに1次発酵、2次発酵、更に3次発酵を実現した、他に類を見ない酵素製品になっています。*一般の酵素製品は、1次発酵、また多くとも2次発酵になります。 更に麹菌発酵大豆イソフラボンにおいては、麹菌で発酵をさせていますので、合計で計4回の発酵を経て製品化しています。 ◆自然の土壌の力で偶然に起こった3次発酵 フローラミーの長期熟成酵素は、1次発酵と2次発酵において、酵母菌と乳酸菌によって85種類の植物を発酵させます。 驚いたことに、その後の製造過程において全く意図せず、他に例のない酢酸菌による「酢酸発酵」が起きました。 調べてみた結果、南米の現地農場の土壌に酢酸菌が含まれていることが分かりました。酢酸菌は、身近なものでは、お酢の製造過程において使用される発酵菌の一つになります。 南米の現地の土壌は、約30年以上かけて熟した果物が熟して落ちて、土に還り、また実っては落ちるということを繰り返し、強い酢酸菌が醸成され、その酢酸菌によって想定外の酢酸発酵が起こりました。 長年にわたり、豊富な果物を無農薬で育ててきたことで、農場の大地は豊かな酢酸菌を含む土壌になっていました。 ◆酢酸発酵の素晴らしい所 酢酸発酵を経ることで、様々なメリットを実現しました。 まずpHが酸性化(pH3.2~pH3.5)することで保存性がアップ。品質が変わることなく、常温での長期保存が可能となりました。酢酸菌には、殺菌効果があり、周りの腐敗菌を殺していくという働きもあります。 また風味、香り、消化吸収力の高まり、更には熱にも強いという利点もあります。 気になるフローラミーの味は、酢酸により少し酸味のある味になっていますが、水と混ぜて摂ることで「思っていたよるみ飲みやすい!美味しい!」という声をよく頂きます。 酵素製品で酸味があり、ほのかに酸っぱいというとても珍しい酵素ペーストになっています。 ◆まとめ フローラミーは、南米の現地の農場で長い年月をかけて、地場の果物が実っては落ち、実っては落ちを繰り返す中で自然の力で培われた酢酸菌によって、その他の酵素製品には無い3次発酵(酢酸発酵)を実現しています。 酢酸発酵のメリットは、酵素自体が酸性に傾くことで保存性がアップ、殺菌効果があるため周りの腐敗菌を殺菌していきます。 また風味や香り、消化吸収力が高まり、更に熱に強くなるというメリットまであります。 ぜひ一度、他に類を見ない酸味のある酵素、フローラミーを試してみて下さい。 2023年10月12日作成者:FLORA ME 滝口 -----------------------------------------------------------------------------------------------美容や健康に関して質問がある方は、気軽に以下の公式LINEからご連絡を頂ければと思います。 公式LINE 担当 滝口
他に類を見ない酵素ペーストでの3次発酵を実現!
一般的に酵素ぺーストや酵素ドリンクは、発酵や熟成によって作られますが、その品質は様々で中には、自然の発酵ではなく、人工的に発酵を早め、熟成期間も1ヶ月しかないというような製品もあります。 反対にフローラミーは、自然の力に任せて、8年にも及ぶ熟成期間を経て作られています。 熟成期間に入る前までに1次発酵、2次発酵、更に3次発酵を実現した、他に類を見ない酵素製品になっています。*一般の酵素製品は、1次発酵、また多くとも2次発酵になります。 更に麹菌発酵大豆イソフラボンにおいては、麹菌で発酵をさせていますので、合計で計4回の発酵を経て製品化しています。 ◆自然の土壌の力で偶然に起こった3次発酵 フローラミーの長期熟成酵素は、1次発酵と2次発酵において、酵母菌と乳酸菌によって85種類の植物を発酵させます。 驚いたことに、その後の製造過程において全く意図せず、他に例のない酢酸菌による「酢酸発酵」が起きました。 調べてみた結果、南米の現地農場の土壌に酢酸菌が含まれていることが分かりました。酢酸菌は、身近なものでは、お酢の製造過程において使用される発酵菌の一つになります。 南米の現地の土壌は、約30年以上かけて熟した果物が熟して落ちて、土に還り、また実っては落ちるということを繰り返し、強い酢酸菌が醸成され、その酢酸菌によって想定外の酢酸発酵が起こりました。 長年にわたり、豊富な果物を無農薬で育ててきたことで、農場の大地は豊かな酢酸菌を含む土壌になっていました。 ◆酢酸発酵の素晴らしい所 酢酸発酵を経ることで、様々なメリットを実現しました。 まずpHが酸性化(pH3.2~pH3.5)することで保存性がアップ。品質が変わることなく、常温での長期保存が可能となりました。酢酸菌には、殺菌効果があり、周りの腐敗菌を殺していくという働きもあります。 また風味、香り、消化吸収力の高まり、更には熱にも強いという利点もあります。 気になるフローラミーの味は、酢酸により少し酸味のある味になっていますが、水と混ぜて摂ることで「思っていたよるみ飲みやすい!美味しい!」という声をよく頂きます。 酵素製品で酸味があり、ほのかに酸っぱいというとても珍しい酵素ペーストになっています。 ◆まとめ フローラミーは、南米の現地の農場で長い年月をかけて、地場の果物が実っては落ち、実っては落ちを繰り返す中で自然の力で培われた酢酸菌によって、その他の酵素製品には無い3次発酵(酢酸発酵)を実現しています。 酢酸発酵のメリットは、酵素自体が酸性に傾くことで保存性がアップ、殺菌効果があるため周りの腐敗菌を殺菌していきます。 また風味や香り、消化吸収力が高まり、更に熱に強くなるというメリットまであります。 ぜひ一度、他に類を見ない酸味のある酵素、フローラミーを試してみて下さい。 2023年10月12日作成者:FLORA ME 滝口 -----------------------------------------------------------------------------------------------美容や健康に関して質問がある方は、気軽に以下の公式LINEからご連絡を頂ければと思います。 公式LINE 担当 滝口

麹菌発酵大豆イソフラボンの健康力について
麹菌発酵大豆イソフラボンは、様々な研究機関との共同研究を通して、その健康増進また、美容への効果性が研究をされて来ました。 その中には、アメリカのハーバード大学との共同研究も含みます。 今回は、麹菌発酵大豆イソフラボンや大豆イソフラボンの研究の一部をご紹介します。 ◆更年期症状の代表的症状を緩和 約10年にもおよぶ更年期、女性ホルモンの「エストロゲン」の急激な減少によって心身両方に特有の不調が現れます。 例えば、「顔がほてる」「汗をかきやすい」「腰や手足が冷えやすい」「くよくよしたり、憂うつになる」「疲れやすい」など。 その①「植物性エストロゲン」とも呼ばれる大豆イソフラボンの臨床試験では、更年期指数がホルモン補充療法とほぼ同等に改善されたケースも認められています。*1 その②突然顔がほてって汗が出るホットフラッシュの症状において、アメリカの研究で麹菌発酵大豆イソフラボンを12週間摂取したところ、ホットフラッシュの症状の頻度や程度が緩和したという報告もあります。出典2 その③エストロゲンを司る脳の視床下部は交感神経と副交感神経を切り替える場所でもありますが、切り替えがうまくいかないと緊張状態が続き、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりもします。そこで、アグリコン型のイソフラボンを摂取して8週間後に不眠スコアが改善したというデータもあります。出典3 ◆健康と美肌に働き、アンチエイジング その①身体の副腎で作られる「DHEA-s」というホルモンがあります。DHEA-sは、若返りホルモンやアンチエイジングホルモンと呼ばれ、肌や筋肉、骨の健康、体脂肪をつきにくく、免疫力アップを担っています。加齢と共に減少をしますが、イソフラボンには、DHEA-sを増やす働きが認められています。 麹菌発酵大豆イソフラボンを1日40mg、3か月間摂取したところ、DHEA-sの血中濃度が3倍に増えることが確認されました。出典4 その②イソフラボンには、美肌効果があり、コラーゲンやヒアルロン酸の産生を促進します。更にイソフラボンの持つ抗酸化作用によって、コラーゲンの酸化・分解を抑制します。 閉経後の女性を対象とした臨床試験にて、麹菌発酵大豆イソフラボンを6週間摂取したところ、メラニン量とシワの本数の改善が認められました。出典5 ◆冷えと血流を改善し、妊活をサポート その①身体の冷えで悩まれる女性は多くいらっしゃいますが、その原因の一つが血の巡りが悪いことだと考えられています。 麹菌発酵大豆イソフラボンには、血小板の凝縮を抑制する働きが認められており、アグリコン型イソフラボンを摂取すると血液がサラサラになる効果があります。出典6 この血流改善こそが、不妊対策の基本となります。妊娠しやすい身体を作るには、ホルモンバランスを整えるほか、抗酸化作用の高いものを摂取したり、血流をよくして冷えを改善することが大切です。 その②着床には、いくつかのサイトカイン(細胞間情報物質)が必要となり、代表的なものはLIFとTGF-βになります。子宮内膜細胞に麹菌発酵大豆イソフラボンを添加したところ、LIFが12倍、TGF-βは5倍に増加し、更に受精卵が着床するときに接着剤のような働きをするグリコデリンタンパク質も増加したことが研究で報告されています。出典7 【まとめ】 麹菌発酵大豆イソフラボン、また大豆イソフラボンには、更年期症状の緩和や改善に限らず、美肌やアンチエイジング、更には冷えや血流を改善し、妊活をサポートする効果まで研究で確認がされています。 ぜひこのような健康や美肌の効果が期待できる、大豆イソフラボンを含んだ大豆製品を積極的に食べていきましょう。 お味噌、納豆、豆腐、醤油、豆乳など日本で昔から愛される食材で健康に美しくなっていきましょう。 美と健康。今日から腸から。頑張っていきましょう!2023年9月30日作成者:FLORA ME 滝口 出典1:日本女性医学学会雑誌(2012)出典2:麹菌発酵大豆イソフラボンの秘密(書籍)出典3:日本産婦人科学会 神奈川地方部会 会誌(2005)出典4:日本産婦人科学会 神奈川地方部会 会誌(2005)出典5:健康・栄養食品研究(2009)出典6:麹菌発酵大豆イソフラボンの秘密(書籍)出典7:Journal of Endocrinology(2008) ------------------------------------------------------------------------------------------------美容や健康に関して質問がある方は、気軽に以下の公式LINEからご連絡を頂ければと思います。...
麹菌発酵大豆イソフラボンの健康力について
麹菌発酵大豆イソフラボンは、様々な研究機関との共同研究を通して、その健康増進また、美容への効果性が研究をされて来ました。 その中には、アメリカのハーバード大学との共同研究も含みます。 今回は、麹菌発酵大豆イソフラボンや大豆イソフラボンの研究の一部をご紹介します。 ◆更年期症状の代表的症状を緩和 約10年にもおよぶ更年期、女性ホルモンの「エストロゲン」の急激な減少によって心身両方に特有の不調が現れます。 例えば、「顔がほてる」「汗をかきやすい」「腰や手足が冷えやすい」「くよくよしたり、憂うつになる」「疲れやすい」など。 その①「植物性エストロゲン」とも呼ばれる大豆イソフラボンの臨床試験では、更年期指数がホルモン補充療法とほぼ同等に改善されたケースも認められています。*1 その②突然顔がほてって汗が出るホットフラッシュの症状において、アメリカの研究で麹菌発酵大豆イソフラボンを12週間摂取したところ、ホットフラッシュの症状の頻度や程度が緩和したという報告もあります。出典2 その③エストロゲンを司る脳の視床下部は交感神経と副交感神経を切り替える場所でもありますが、切り替えがうまくいかないと緊張状態が続き、寝つきが悪くなったり、眠りが浅くなったりもします。そこで、アグリコン型のイソフラボンを摂取して8週間後に不眠スコアが改善したというデータもあります。出典3 ◆健康と美肌に働き、アンチエイジング その①身体の副腎で作られる「DHEA-s」というホルモンがあります。DHEA-sは、若返りホルモンやアンチエイジングホルモンと呼ばれ、肌や筋肉、骨の健康、体脂肪をつきにくく、免疫力アップを担っています。加齢と共に減少をしますが、イソフラボンには、DHEA-sを増やす働きが認められています。 麹菌発酵大豆イソフラボンを1日40mg、3か月間摂取したところ、DHEA-sの血中濃度が3倍に増えることが確認されました。出典4 その②イソフラボンには、美肌効果があり、コラーゲンやヒアルロン酸の産生を促進します。更にイソフラボンの持つ抗酸化作用によって、コラーゲンの酸化・分解を抑制します。 閉経後の女性を対象とした臨床試験にて、麹菌発酵大豆イソフラボンを6週間摂取したところ、メラニン量とシワの本数の改善が認められました。出典5 ◆冷えと血流を改善し、妊活をサポート その①身体の冷えで悩まれる女性は多くいらっしゃいますが、その原因の一つが血の巡りが悪いことだと考えられています。 麹菌発酵大豆イソフラボンには、血小板の凝縮を抑制する働きが認められており、アグリコン型イソフラボンを摂取すると血液がサラサラになる効果があります。出典6 この血流改善こそが、不妊対策の基本となります。妊娠しやすい身体を作るには、ホルモンバランスを整えるほか、抗酸化作用の高いものを摂取したり、血流をよくして冷えを改善することが大切です。 その②着床には、いくつかのサイトカイン(細胞間情報物質)が必要となり、代表的なものはLIFとTGF-βになります。子宮内膜細胞に麹菌発酵大豆イソフラボンを添加したところ、LIFが12倍、TGF-βは5倍に増加し、更に受精卵が着床するときに接着剤のような働きをするグリコデリンタンパク質も増加したことが研究で報告されています。出典7 【まとめ】 麹菌発酵大豆イソフラボン、また大豆イソフラボンには、更年期症状の緩和や改善に限らず、美肌やアンチエイジング、更には冷えや血流を改善し、妊活をサポートする効果まで研究で確認がされています。 ぜひこのような健康や美肌の効果が期待できる、大豆イソフラボンを含んだ大豆製品を積極的に食べていきましょう。 お味噌、納豆、豆腐、醤油、豆乳など日本で昔から愛される食材で健康に美しくなっていきましょう。 美と健康。今日から腸から。頑張っていきましょう!2023年9月30日作成者:FLORA ME 滝口 出典1:日本女性医学学会雑誌(2012)出典2:麹菌発酵大豆イソフラボンの秘密(書籍)出典3:日本産婦人科学会 神奈川地方部会 会誌(2005)出典4:日本産婦人科学会 神奈川地方部会 会誌(2005)出典5:健康・栄養食品研究(2009)出典6:麹菌発酵大豆イソフラボンの秘密(書籍)出典7:Journal of Endocrinology(2008) ------------------------------------------------------------------------------------------------美容や健康に関して質問がある方は、気軽に以下の公式LINEからご連絡を頂ければと思います。...

吸収率が通常の3倍?? 麹菌発酵大豆イソフラボンとは
前回のコラムで大豆イソフラボンについて紹介をしました。まだ読まれていない方は、そちらをCHECKしてみて下さい。 前回コラム「女性の強い味方、大豆イソフラボン!」 大豆イソフラボンが優れた機能を持つことは、前回のコラムで紹介しましたが、実はそのままでは体内に吸収されにくいという難点があります。 【アグリコン型 イソフラボンとは】 イソフラボンには、分子が大きい「グリコシド型イソフラボン」と分子から糖が分解されて身体に吸収されやすい「アグリコン型イソフラボン」という種類があります。 実は一般的なイソフラボンは、グリコシド型になり、身体に吸収されるまでに腸内細菌によって糖を分解する必要があり、吸収されるまでにひと手間かかってしまいます。例えば、豆腐や納豆や豆乳がそれにあたります。 それに比べてアグリコン型イソフラボンは、既に糖が分解されていることから、身体への吸収がスムーズでグリコシド型イソフラボンに比べて約3倍吸収率が高くなります。例えば、醤油や味噌にアグリコン型イソフラボンが多く含まれます。 イソフラボンから美容と健康の効果を得るためには、アグリコン型イソフラボンを摂った方が、効率的と言えますね。 【麹菌発酵大豆イソフラボンとは】 麹菌発酵大豆イソフラボンは、大豆イソフラボンを麹菌によって発酵させることで、糖を分解し身体に吸収されやすい「アグリコン型イソフラボン」にしたものになります。 糖が分解されており、吸収率は約3倍と紹介しましたが、実は吸収スピードも約3~4倍になり、胃や腸からスムーズに取り込まれます。 更に麹菌発酵大豆イソフラボンの「アグリコン型大豆イソフラボン」には「ダイゼイン」「ゲニステイン」「グリシテイン」の3種類のイソフラボンが含まれていますが、その中で特に注目をされているのがダイゼインになります。 ダイゼインは、脂肪細胞を小さくしたり、長寿遺伝子を活性化させたりと様々な効用が確認されています。 【ダイゼインの働き】 ①体内でエクオールを作りだせる エクオールとは、イソフラボンと同じく女性ホルモンに似た働きをする成分になります。このエクオールとは、エクオール産生菌という腸内細菌がダイゼインを食べた後の代謝産物になります。 ダイゼインが豊富に含まれている麹菌発酵大豆イソフラボン(アグリコン型)を摂取すると、腸内で効率よく吸収され、更にエクオールも作られます。 ただ、エクオールを作りだすエクオール産生菌を日本人全員が持っているわけではなく、約50%の作り出せるようです。 ただ、継続的に腸内環境を整える腸活をおこなうことでエクオール産生が生まれやすくなると腸活に期待されています。 ②長寿遺伝子を活性化させる 長寿遺伝子は、サーチュイン遺伝子とも言われ、老化の原因になる活性酸素を除去したり、遺伝子の損傷を防いだりと長寿の可能性を秘めています。 このサーチュイン遺伝子は、ファスティングをしてカロリー摂取を減らし、飢餓状態に陥った時に活性化する性質をもっていることで有名ですが、実はダイゼインもこのサーチュイン遺伝子にスイッチを入れることが出来ると言われています。 日本は昔から醤油や味噌、豆腐など大豆製品を食べる習慣があり、かつ長寿国になっているのは、このダイゼインが一役を担っている可能性もありますね。 ③脂肪細胞を小さくする 動物実験での実験結果として、ダイゼインが豊富なアグリコン型イソフラボンを投与すると脂肪細胞が小さくなったという研究結果も報告されています。 更に少ないインスリン量でも血糖値を抑えられることが明らかになり、糖尿病の予防効果も期待されています。 【まとめ】 麹菌発酵大豆イソフラボン(アグリコン型イソフラボン)は、通常のグリコシド型イソフラボンと比較して、約3倍も身体に吸収されやすく、また美容と健康へのプラスの働きがたくさんあります。 エクオールの産生、長寿遺伝子の活性化、脂肪細胞の小型化など、様々な効果があります。...
吸収率が通常の3倍?? 麹菌発酵大豆イソフラボンとは
前回のコラムで大豆イソフラボンについて紹介をしました。まだ読まれていない方は、そちらをCHECKしてみて下さい。 前回コラム「女性の強い味方、大豆イソフラボン!」 大豆イソフラボンが優れた機能を持つことは、前回のコラムで紹介しましたが、実はそのままでは体内に吸収されにくいという難点があります。 【アグリコン型 イソフラボンとは】 イソフラボンには、分子が大きい「グリコシド型イソフラボン」と分子から糖が分解されて身体に吸収されやすい「アグリコン型イソフラボン」という種類があります。 実は一般的なイソフラボンは、グリコシド型になり、身体に吸収されるまでに腸内細菌によって糖を分解する必要があり、吸収されるまでにひと手間かかってしまいます。例えば、豆腐や納豆や豆乳がそれにあたります。 それに比べてアグリコン型イソフラボンは、既に糖が分解されていることから、身体への吸収がスムーズでグリコシド型イソフラボンに比べて約3倍吸収率が高くなります。例えば、醤油や味噌にアグリコン型イソフラボンが多く含まれます。 イソフラボンから美容と健康の効果を得るためには、アグリコン型イソフラボンを摂った方が、効率的と言えますね。 【麹菌発酵大豆イソフラボンとは】 麹菌発酵大豆イソフラボンは、大豆イソフラボンを麹菌によって発酵させることで、糖を分解し身体に吸収されやすい「アグリコン型イソフラボン」にしたものになります。 糖が分解されており、吸収率は約3倍と紹介しましたが、実は吸収スピードも約3~4倍になり、胃や腸からスムーズに取り込まれます。 更に麹菌発酵大豆イソフラボンの「アグリコン型大豆イソフラボン」には「ダイゼイン」「ゲニステイン」「グリシテイン」の3種類のイソフラボンが含まれていますが、その中で特に注目をされているのがダイゼインになります。 ダイゼインは、脂肪細胞を小さくしたり、長寿遺伝子を活性化させたりと様々な効用が確認されています。 【ダイゼインの働き】 ①体内でエクオールを作りだせる エクオールとは、イソフラボンと同じく女性ホルモンに似た働きをする成分になります。このエクオールとは、エクオール産生菌という腸内細菌がダイゼインを食べた後の代謝産物になります。 ダイゼインが豊富に含まれている麹菌発酵大豆イソフラボン(アグリコン型)を摂取すると、腸内で効率よく吸収され、更にエクオールも作られます。 ただ、エクオールを作りだすエクオール産生菌を日本人全員が持っているわけではなく、約50%の作り出せるようです。 ただ、継続的に腸内環境を整える腸活をおこなうことでエクオール産生が生まれやすくなると腸活に期待されています。 ②長寿遺伝子を活性化させる 長寿遺伝子は、サーチュイン遺伝子とも言われ、老化の原因になる活性酸素を除去したり、遺伝子の損傷を防いだりと長寿の可能性を秘めています。 このサーチュイン遺伝子は、ファスティングをしてカロリー摂取を減らし、飢餓状態に陥った時に活性化する性質をもっていることで有名ですが、実はダイゼインもこのサーチュイン遺伝子にスイッチを入れることが出来ると言われています。 日本は昔から醤油や味噌、豆腐など大豆製品を食べる習慣があり、かつ長寿国になっているのは、このダイゼインが一役を担っている可能性もありますね。 ③脂肪細胞を小さくする 動物実験での実験結果として、ダイゼインが豊富なアグリコン型イソフラボンを投与すると脂肪細胞が小さくなったという研究結果も報告されています。 更に少ないインスリン量でも血糖値を抑えられることが明らかになり、糖尿病の予防効果も期待されています。 【まとめ】 麹菌発酵大豆イソフラボン(アグリコン型イソフラボン)は、通常のグリコシド型イソフラボンと比較して、約3倍も身体に吸収されやすく、また美容と健康へのプラスの働きがたくさんあります。 エクオールの産生、長寿遺伝子の活性化、脂肪細胞の小型化など、様々な効果があります。...